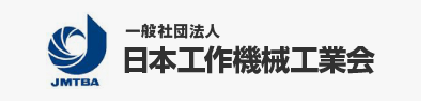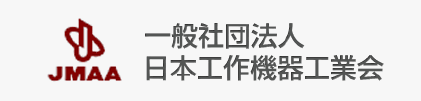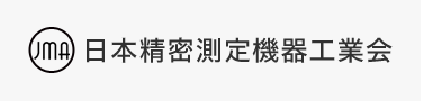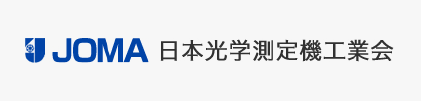前半はこちら 1月5日号の新春座談会・前半はメーカー5社に25年の景況感や変化するユーザーニーズについて聞いた。足元の国内製造業は低迷しているものの、造船、航空・宇宙、防衛、エネルギーなどの業種で回復の兆しがあり、そこへ […]
【特集】労働安全の最前線 ー現場を訪ねてー
明電舎 デジタル(VRやメタバース)活用の安全教育
重電メーカーの明電舎は「安全体感車」による実例を再現度高く模した危険体感に加え、VR(仮想現実)を活用した独自の労働安全教育を進めている。5月には仮想空間「メタバース」を活用した安全教育のシステムを開発するなど、新たなデジタルツールを活かし、労働災害ゼロを目指している。
安全体感車で危険を体感

同社では、重電のインフラ構築を手掛けるため、100以上の工事現場を抱えている。こうした現場では、技能伝承に加え、安全教育が大きな課題だという。「日本は安全対策が進み、危険を実際に経験する機会が減っている」(生産統括本部安全環境管理部の三浦崇副部長)からだ。
こうした課題に対応するには「危険の感受性に訴える教育が必要」とし、2008年から、実際に作業現場での危険を経験できる装置や教育を開始。17年には「安全体感車」(写真①)を開発した。そこでは感電や巻き込まれ、有機溶剤による爆発など、数十種類の危険を実際に体感できる。

車両にしたのは、全国の現場を回る必要があったことに加え、「責任者への教育だけでなく、最前線の現場で働く作業者の方にこそ、経験してもらいたかった」(三浦副部長)からだ。現在は、工事現場と生産現場向けの2台を所有。16年からは社外への展開し、延べ2万7000人以上が受講した。
こうした教育に加え、近年注力するのがVRを活用した体感教育だ。その狙いは、体感車では経験できないことに対応するため。確かに、リアルの世界では、高所から転落したり、クレーンから荷を落としたりといった事故の体感は難しいが、VRならそれも可能だ。
単純に経験して楽しむだけで終わらないように、臨場感を持たせる工夫を凝らしている。採用した3軸VRシミュレータ(写真②)では、モーションプレートが上下左右に動き、振動や衝撃を体感者に伝えるようにした。はしごを上る作業では、プレートが上下し、実際に上っているような感覚が得られる。コンテンツは墜落、火災、衝突などに加え、没入感を追求するため、シネマ型など全部で29種類をそろえた。

デジタル技術では、モーションキャプチャも活用する。カメラで荷物を持ち上げる姿勢を撮影し、運搬動作のモニターをチェック。改善点を指示するなど腰痛対策をサポートする(写真③)。
最近では、こうした安全教育を社外にも開放している。加えて、VRのコンテンツや機器の貸し出しも行う。サブスクリプション(定額課金制)やレンタルで1か月5万5000円(税抜)から活用できるという。(1コンテンツに対しパソコン、ヘッドマウントディスプレーのレンタルが必要)。
今後もデジタルを活用した安全教育を強化する考えだ。5月にはメタバースを活用した教育システムを開発。受講者がアバターとなって、メタバース上で危険を実体験できる。また、VR空間に実写を差し込むことで手に持ったコントローラで操作ができるような「実機訓練AR」などの採用も考えているという。「今後もキャプチャーやVRなどデジタル技術を活かし、労災ゼロを目指したい」(三浦副部長)。
関連特集記事は、以下のリンクから
日本産機新聞 2022年9月20日
日本工作機械輸入協会 金子一彦会長「連携強め、ソリューション提供」 昨年の工作機械輸入通関実績は約667億円となった。円安がさらに進んだ傾向にあり、 私たち輸入関連事業者にとっては、非常に厳しい試練の年だった。 今年は国 […]
日本工作機械工業会 坂元繁友会長「工作機械受注1兆7000億円」 2025年の工作機械受注額は年初見通しの1兆6000億円をわずかながら下回る見込みだ(速報値では1兆6039億円)。政治的リスクが顕在化する中で、高い水準 […]