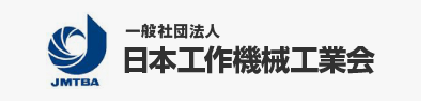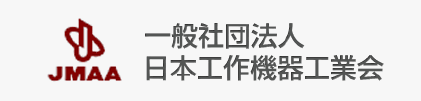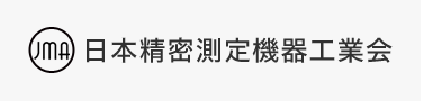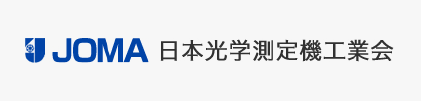真のグローバル企業に/売上高1000億円目指す 今年3月、ソディックは、圷祐次副社長が代表取締役CEO社長執行役員に就く人事を発表した。欧米経験が長い圷社長は自身のミッションを「ソディックを真のグルーバル企業にすること」 […]
【商社トップインタビュー】ユアサ商事/濱安 守取締役
コロナ禍によるデジタル活用の加速から始まり、半導体をはじめとしたモノ不足や素材の高騰、混乱が続くウクライナ情勢などの諸問題は収束の兆しが見えず、先行きの見通しはますます難しくなっていく。さらにカーボンニュートラル(CN)やSDGsといった社会課題への対応も求められており、経営環境の変化はまだまだ続くだろう。それらの変化の中で、機械工具卸商社は何を重視し、どのように対応していくのか。今年注力することについて、15社に聞いた。

顧客の本質的課題を把握
今年注力することは。
抽象的だが、「マーケットに寄り添う」意識を高めることに注力したい。2026年に売上高6000億円を目標とする「ユアサビジョン360」の達成に向けても、製造業の急速な変化を考えても、そうした姿勢を持つことが重要になる。
製品の供給なのか、サービスや補修なのか、ソリューションの提案なのか。マーケットを知り、ユーザーが本当に必要とする機能を提供しなければいけない。
そう思うのはなぜか。
カーボンニュートラルが起点となり、自動車の電動化、半導体需要の拡大、エネルギー問題と3つのパラダイムシフトが起きている。この変化に対応するには従来のやり方では通用しないからだ。
例えば「半導体製造現場が好調だからそこに機械を売ろう」と言っているようではダメ。半導体業界の本質的な課題を掴み、その改善を提案する。また、自らの利益や都合だけで提案するプロダクトアウト的な発想も変えなくてはいけない。マーケットイン的な発想で、ユーザーの本当の課題を知る必要がある。
卸商社はユーザーからは遠く、マーケットに近づくのは難しいのでは。
その通りだが、我々は卸商社のスタンスでマーケットにアプロ—チしていきたい。そのために、例えば販売店と一緒にユーザーに訪問できる機能や能力を持つ必要がある。
その機能や能力とは。
エンジニアリングやマーケティングがそうだ。各部署や子会社に点在する50人以上のエンジニアやマーケティングスタッフを融合させ、効率的にその能力を提供する仕組みも考えている。
また、パラダイムシフトによって、顧客が求めることも広がり、機械は機械部、工具は機電部という時代ではなくなる。機械や工具、物流、制御を扱う当事業本部の枠組みさえ変える必要があるのかもしれない。今はそれだけ変化が大きいということだ。
日本産機新聞 2022年7月20日
回転スピード3段階/車のタイヤ、効率良く取付け ベッセル(大阪市東成区、06・6976・7771)は、回転モードを切り替えることで自動車のタイヤを効率良く取付けられる充電インパクトレンチを発売した。自動車組立・整備工具の […]
レヂボン水魚会 支部総会を開催 日本レヂボン(大阪市西区、06・6538・0136)は6月10日、宝塚ホテル(兵庫県宝塚市)で関西支部と中・四国支部合同のレヂボン水魚会支部総会を開いた。グループ企業との連携による海外市場 […]