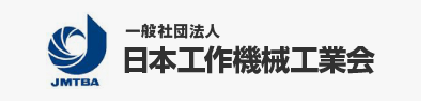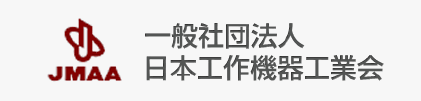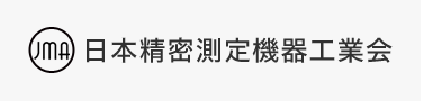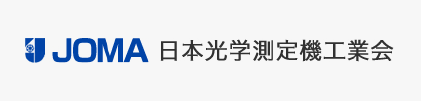前向きな思考、自由な発想 「営業所長はアイデアマンでないといけない。どうすれば営業所の営業力を高められるか。どのように新商品を的確にユーザーにPRし受注に結び付けるか。様々な角度からアイデアを出し成功へと導く。それが所長 […]
自力成長軌道へ

今年は、改革・変革の手を緩めることなく、さらに手を打ち続けたい。業績が堅調な今だからこそ、周囲のあらゆる環境に左右されず、行政政策に頼らずに実力で成長できる堅固な経営体質を築き上げたい。その絶好のチャンスが今年ではないだろうか。
機械工具業界は、自社の得意分野や環境に応じて、事業の水平展開・垂直展開、拠点政策など各社各様の取り組みを行っている。リーマンショック後の低迷から回復している今、油断をしたくない。ここで変革の手を緩めることなく、継続的にチャレンジする時だ。
変化が激しい今の時代に適合し、成長し続けるのに立ち止まることは許されないだろう。自力で成長できる自社なりのビジネスモデルを築くことを目指したい。


2015年の機械工具業界は概ね良い業績を残すことができた。特に工作機械の国内受注が回復した。1~11月の11か月累計(速報)でみると、総受注額は前年同期比0・6%増の1兆3734億円で、うち内需は同21・3%増の5436億円、外需は同9・5%減の8297億円となった。海外、特に中国市場が鈍化する中で、国内の工作機械受注は好調に推移した。
工場の稼働率を反映する切削工具も堅調を維持。特殊鋼工具の1~10月の累計生産額が前年同期比4・3%増の746億円、超硬工具のそれは同8・1%増の2323億円となり、最終ユーザーの生産現場の忙しさを映し出した。
国内好調の要因は、自動車産業を中心に設備投資が旺盛で、中小企業の投資意欲の回復も大きかったことが挙げられる。一方で、安倍晋三政権が進めるアベノミクスの一環である設備投資への補助金や減税措置などの政策的な後押しの影響も大きい。


2016年は、どうか。工作機械は横ばいあるいは微増と見る声と、減速を懸念する声が交錯している。国内では補助金や減税措置による一層の需要掘り起こし(次代に向けたチャレンジ投資や更新需要など)への期待もある。工作機械需要の60%を占める自動車・自動車部品産業は、新モデルや環境車開発投資、さらには新規に参入する動きも出ている。ロボットを活用した自動化・無人化の進化・普及も加速しそうだ。今秋に開催されるJIMTOFでは、展示スペースが約11000㎡拡大され、出展者が大幅に増えて盛り上がりが期待される。
ただし、新興国の減速や米国の利上げなど不安要素も見過ごせない。ネット通販への危機感を言う人も多い。予想が交錯する所以だが、機械工具流通業界としては引き続き堅調に推移すると見たい。
ヤマト運輸の小倉昌男元社長は「デメリットのあるところにこそ、ビジネスチャンスがある」と言っていた。郵便という明治以来の制度と既得権益、官僚という巨大で高い壁をぶち破り、顧客の本当の要望を掴んで、宅配便事業を成功させた。
郵便局という巨人、官僚という壁に闘いを挑むという勇気と忍耐は相当なものだったと推測する。
今一度、得意先が喜ぶであろうことを思いつつ、頭から「無理だ」と諦めないで、計画することすら思いもよらなかったことを見つめ、根元から考え直してみたい。
常識を「当たり前」とせず、その「目的」と「手段」を「ゼロベース」でシミュレーションし直ししてみてはどうだろうか。
大きな壁の向こうに新しい事業展開が見えてくる。期待する1年である。
日本産機新聞 平成28年(2016年)1月5日号
スマートファクトリーに注力/システムつなぎ、一気通貫で提案 NTTデータエンジニアリングシステムズは2025年7月、金型向けCAD/CAM「Space‐E」などを手掛ける製造ソリューション事業とクラウド事業を分社化し、新 […]
ワンストップソリューションを強化 直動機器や減速機、モーター、ドライバー・コントローラー、産業用ロボットなど幅広く手掛けるハイウィン(神戸市西区、078・997・8827)は需要が増している自動化・省人化提案を強化するた […]