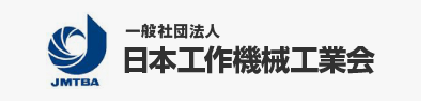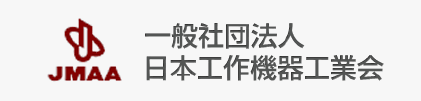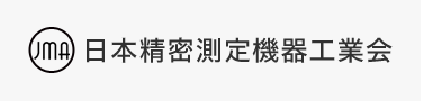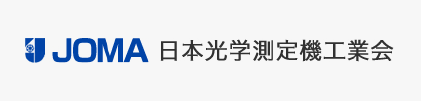前半はこちら 1月5日号の新春座談会・前半はメーカー5社に25年の景況感や変化するユーザーニーズについて聞いた。足元の国内製造業は低迷しているものの、造船、航空・宇宙、防衛、エネルギーなどの業種で回復の兆しがあり、そこへ […]
人事評価制度を独自工夫 結果はプロセスにある 〜仕事考〜
テレワークの活用
働き方が加速度的に変わった。大手企業を中心にテレワークの導入が進み、在宅しながら会社にかかってくる電話の受信・転送システムを導入したり、事務所を縮小し固定費を削減するところも。一方「テレワークを行える業務ではない」という理由で導入していないという声も。機械工具業界でも導入している企業があるが、なかなか増えない。出社組とテレワーク組が混在している企業が大半だろう。
テレワークで難しいのは、各メンバーの仕事ぶりが見えないこと。Eメール、Zoom、TeamsなどICTを使ったコミュニケーションは、否応なく増えた。一方で、ちょっとした相談や気付いたときの何気ないフォロー、一杯やりながらの相談など、チームとして仕事の生産性を向上するというリアルの昭和人間的コミュニケーションが取れない。
人事評価システムが課題ではないか。テレワーク中の評価を、上司は公平・公正にするか、さぼっていると思われていないか…など不安を持つ。
多くの企業が目標管理制度を導入しているが、成果主義だけでは不十分。上司と部下が目標を共有し、結果だけでなくシナリオと各プロセスの目標(数値や定性的目標)をできるだけ細分化して頻繁に評価することで、出社組・テレワーク組関係なく公正な評価ができないだろうか。例えば、スケジューラーの活用。自分以外のメンバーのスケジュールもリアルタイムで見ることができる。時間単位(例えば2時間単位)で仕事内容と達成目標まで記入しておけば、上司や同僚からもアドバイスがもらえるかも。しっかりスケジュール管理をして、日報で報告すれば…と考えてみる。
テレワークは、感染症リスクを減らす以外に、通勤・移動にかかる時間を削減、ペーパーレス化の進展などメリットも多い。就業規則で職種を限定する方法もある。生産性の向上をこの機会に見直すことも必要になる。コスト削減、感染症対策など目的を明確にし、独自の導入方法を検討してみてはどうだろう。
日本産機新聞 2021年9月20日
日本工作機械輸入協会 金子一彦会長「連携強め、ソリューション提供」 昨年の工作機械輸入通関実績は約667億円となった。円安がさらに進んだ傾向にあり、 私たち輸入関連事業者にとっては、非常に厳しい試練の年だった。 今年は国 […]
日本工作機械工業会 坂元繁友会長「工作機械受注1兆7000億円」 2025年の工作機械受注額は年初見通しの1兆6000億円をわずかながら下回る見込みだ(速報値では1兆6039億円)。政治的リスクが顕在化する中で、高い水準 […]